交通インフラが担う使命と地域に愛されるデザインを両立す
社名:九州旅客鉄道株式会社
URL:https://www.jrkyushu.co.jp/
本社:福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号
創業:1987(昭和62)年4月1日
代表取締役:古宮洋二
事業内容:旅客鉄道事業/旅客自動車運送事業/旅行業/駐車場業/広告業/損害保険代理業その他の保険媒介代理業/旅行用品、飲食料品、酒類、医薬品、化粧品、日用品雑貨等の小売業/旅館業及び飲食店業/不動産の売買、賃貸、仲介及び管理業

「BRTひこぼしライン」からSketchUpの本格稼働
平成29年7月5日から6日にかけて、九州北部を襲った豪雨(平成29年7月九州北部豪雨)は、福岡県と大分県を中心に記録的な降水量をもたらし、甚大な被害を引き起こした。
鉄道網への影響も甚大で、特に九州旅客鉄道(JR九州)が運行する日田彦山線では橋梁の流失や線路の損壊が発生し、一部区間では運行が不可能となった。
再開に向け、沿線地方自治体とJR九州は協議を重ね、結果、バス高速輸送システム(BRT:Bus Rapid Transit)での復旧が決定。2023年8月28日、日田彦山線添田駅と夜明・日田駅を結ぶ約40kmの「日田彦山線BRT」(愛称:BRTひこぼしライン)が開通した。

運行中のBRT。外観は「おりひめの羽衣」をイメージしており、現在稼働している7台のBRTにはそれぞれ、
東峰村の「棚田」や日田市の花「あやめ」などから連想したカラーリングが施されている
日田彦山線の復旧は喜ばしいが、地域のシンボルとして慣れ親しんできた路線の一部がBRTに置き換わることへの、自治体や住民の戸惑いは想像に難くない。「『鉄道で復旧してほしい!』と願う住民の方々の気持ち、線路が道路に変わり、バスが通ることへの複雑な感情」には、JR九州の社員ながら共感できたと、(当時)建設工事部に所属していた永松博晶氏は振り返る。それでも、「せっかくBRTとして再開するなら、地域の人たちに親しみ、楽しんでもらえる交通機関にしたい」という社内の思いから、社内の建築系社員有志によってブランディングデザインを行う気運が生まれた。手を挙げた十数名が4、5人ずつのチームに分かれ、手始めとしてBRTのロゴデザインや待合ブースのデザインを提案して競うことになった。この社内コンペティションでは、事務局側から「提案には3Dモデルを十分に活用すること」との指示があり、この「3Dモデル」という前提条件によって、「BRTひこぼしライン」デザインプロジェクトどころか、その後の同社の建築設計やデザイン提案業務の先行きをがらっと変える印象的な体験があったと永松氏は言う。

鉄道事業本部工務部設備課の永松博晶氏
メンバーの一人が、当時の職場では少数の使用にとどまっていたSketchUpとレンダリングソフトのPodiumを使って、「こんなのを作ってみたんだけど、どうだろうか」とCGパースを披露した(下図)。メンバー曰く、長さや厚みが異なる木材を組み合わせ、沿線の山々が重なり連なる山並みを、待合ブースに表現したのだという。

BRTひこぼしラインの起終点となる添田駅に設置された待合ブースのデザイン案(左)と竣工写真。待合ブースは7つの駅に設置されている
数年を経た今なお、永松氏が「一番感動したのがこれ!」と熱っぽく語るほど、当時は相当なインパクトがあったのだろう。コンセプトやモチーフ、フォルムへの想い入れ、素材へのこだわりが、CGパースにぎゅっと集約され雄弁に語る。そして光や影、質感が表現されたリアルなレンダリングによる説得力――。このCGパースがもとになって、メンバーらの創作意欲やモチベーションが大いに刺激され、互いに切磋琢磨するきっかけとなった。
社内や自治体などの関係者も招いて行われた社内コンペの発表会では好評を得たうえ、「ここまでやれるなら、『BRTひこぼしライン』のブランディングデザインも建築系社員に担当してもらおうじゃないか」という流れになり、BRTのロゴデザインや待合所の他、ひいてはBRT車両の内外装デザインまで手掛けることになった。

BRTひこぼしラインの専用サイト。社内コンペのメンバーらが考えたデザインコンセプトやロゴマークなどが掲載されている
大型案件やプロジェクトはテーブル単位で担当
今回取材に応じてくれたのは、4月から工務部設備課に所属する入社13年目(2025年2月取材時)の永松氏、建設工事部施設課の濵田菜波氏、木原悠佳氏の3人。
永松氏が所属する設備課は、駅舎をはじめ上家(乗降客を風雪から守るホーム上の建造物)や信号通信機器室などの鉄道関連施設のほか、社員が働くオフィス建物などの計画や他部署との調整が主業務だ。計画テーブルに属する永松氏はSketchUpなどの3Dツールを使い、社内の合意形成や社外向けの提案資料の作成を担当している。
一方、施設課は工事を発注する部署で、濵田氏と木原氏がともに所属する建築テーブルは計画案を基に設計や施工の発注・マネジメント業務を担う。入社5年目の濵田氏は、新駅や駅改良工事のほか、自治体から受託した(駅構内を横断する)自由通路の工事など、社内外の案件を担当している。前述の「BRTひこぼしライン」の社内コンペには入社1年目から、永松氏とは別チームで参加しながら、本業務へのSketchUp本格導入のテストユーザーも務めたほか、現在、同社が推進しているBIM(Building Information Modeling)にもかかわっている。入社1年目の木原氏は、自社資金で行う工事、たとえば駅構内トイレの改良・改修などを中心に担当する。
計画テーブル、建築テーブルとは、同社が採用している「テーブル」制のひとつで、各テーブルにはテーブルマスターのほか4、5人の建築系社員が所属する。各テーブルに割り振られた大型案件や各種プロジェクトは、主にテーブルマスターと各担当社員で業務を遂行していくのだという。
駅舎の地域性を活かした「恋するトイレプロジェクト」
濵田氏、木原氏が現在担当している案件や建築テーブルで取り組んでいるプロジェクトを見せてもらう。

建設工事部施設課の濵田菜波氏。SketchUpで簡易的に作った3Dモデルで取引会社とイメージをすり合わせたり、
BIMを進めている建築物の納まりをSketchUpでモデリングして施工会社に説明したりしている
濵田氏がデモンストレーションしてくれたのは、職場環境改善活動の一環で行われた自社オフィスのリニューアル工事だ。線路の高架下という特殊な立地条件から、フロアは幅が狭く、縦が極端に長い。コロナ禍を契機に導入されたフリーアドレス制に最適化したレイアウトや動線の実現も期待された。
たとえば、「デスクワークに集中できるエリアがほしい」という社員の声には、集中して作業したい人向けのスペースを窓際に設けた。「気軽にミーティングしたい」というリクエストには、フロア中央を貫く通路沿いにキャビネットを島状に配置。キャビネットには大判の資料を広げられる天板を載せ、立った状態で打ち合わせられるようにした。このように社員から寄せられた要望や既存オフィスへの不満を検討し、数パターンのレイアウトをSketchUpでモデリングして、什器を配置した状態で社員たちに見てもらった。空間や使い勝手をよりリアルに感じてもらうため、ウォークスルームービーも制作して意見や感想を募り、レイアウト案にフィードバックしていった。

自社オフィスのリニューアル案を検討するために制作されたウォースルームービの一場面。
平屋軽量鉄骨造の建物には建設工事部が入居する
2024年初頭から3か月かけて工事が行われ、新レイアウトによるオフィスが本格稼働したのは4月。「自分たちの勤務先を自ら設計し改良するプレッシャーは大きかった」と濵田氏は心情を吐露するが、社員たちの声を丹念に吸い上げたレイアウトは高評価を得ているようだ。

建設工事部施設課の木原悠佳氏
木原氏がデモしてくれた「恋するトイレプロジェクト」は、「駅舎のトイレが快適でない」という利用者の声に応え、JR九州管区内の駅舎のトイレを順次リニューアルするというもので、古宮洋二JR九州社長肝入りの案件だ。プロジェクトには建築テーブルのメンバーらが総力を挙げて取り組んでいる。


博多駅中央改札内トイレ計画時のCGパース(上)と竣工写真。
福岡の伝統工芸品である博多織と博多曲物をモチーフにデザインされた。
「恋するトイレプロジェクト」による改良工事は随時実施中だ
上図はプロジェクト第1弾として2024年12月27日にリニューアルオープンした博多駅中央改札内トイレだ。上が計画段階でSketchUpやRevitとレンダリングソフトTwinmotionを用いて作成されたCGパース、下が竣工写真だ。

各駅舎トイレの計画過程では、当地の観光名所や特産物などを手掛かりに「地域性」を設定し、それをもとにデザイン展開しているという。博多駅は博多地区特産の絹織物「博多織」から、香椎駅では夫婦の宮「香椎宮」の蔀戸(しとみと)の緑青塗りから着想したデザイン、といった具合だ(ちなみに、入力したキーワードから連想される3DイメージをAI生成するSketchUpのDiffusion機能はこうした用途に非常に向くだろう。)
目を引くのは、CGパースに壁や床面、照明などの仕上げを直接書き込み、施工用の資料としても活用している点だ。「たとえば、3Dで可視化したメラミン化粧板に品番も添えておけば、施工図よりも直感的にわかります。このプロジェクトでは仕上げを木調で統一しながら、木調の色・柄は各駅で異なるので、そこも明確になるよう意識しています」。博多駅の男性用トイレで(壁面の帯状の布素材として)博多織を使い、「なぜその位置にダウンライトを配置するのかといった意図をCGパースで実際に見て納得してもらい、計画を理解してもらう」ためだと木原氏は言う。
「BRTひこぼしライン」や「恋するトイレプロジェクト」、自社オフィスリニューアルとも共通するのは、キーワードやシンボルを手掛かりに、アイデアを練り上げてイメージに昇華しフォルムとして具現化する手法が採用されていること。さらに、このプロセスは3Dとして可視化され、各種媒体を通じてJR九州発のニュースリリースとして広く公開されていることだ。
「従来は完成するまで全体像を把握できないことが多かったのですが、SketchUpを活用することで、初期段階から全体を視覚化できるようになりました。これにより、早い段階で『こうしたほうがよいのでは』といった議論が可能になり、3Dモデルを効果的に活用できるようになりました。特に、駅のような公共性が高い施設では、お客様さまに楽しんでいただける空間を提供することや、地域性を反映させることも重要だと考えています。このような高いレベルでの駅舎空間づくりが実現できれば理想的です」と永松氏は語る。交通インフラの構築や整備という本業をおさえつつ、利用者や地域住民に地域の魅力を伝え、日々の暮らしに楽しさや明るさを添える挑戦を続けるJR九州の取り組みに今後も注目していきたい。
-
 交通インフラが担う使命と地域に愛されるデザインを両立す…
交通インフラが担う使命と地域に愛されるデザインを両立す…
2025.04.17
JR九州 社名:九州旅客鉄道株式会社 URL:https://www.jrkyushu.co.jp/ 本社:福岡
-
 ミニマルなBIMへの意欲的なチャレンジは 手痛い失敗と反省か…
ミニマルなBIMへの意欲的なチャレンジは 手痛い失敗と反省か…
2024.08.27
フレイム一級建築士事務所 社名:株式会社フレイム URL:https://frame1.co.jp/ 創業:19
-
 アナログ人間の堂宮大工が挑む歴史的建造物のデジタル化への期待…
アナログ人間の堂宮大工が挑む歴史的建造物のデジタル化への期待…
2024.08.01
岩瀬社寺建築 社名:岩瀬社寺建築株式会社 URL:https://www.facebook.com/Iwases

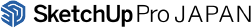





<株式会社アルファコックス>
建築・土木・インテリア関連CG・
3Dモデルソフトウェアの販売・サポート